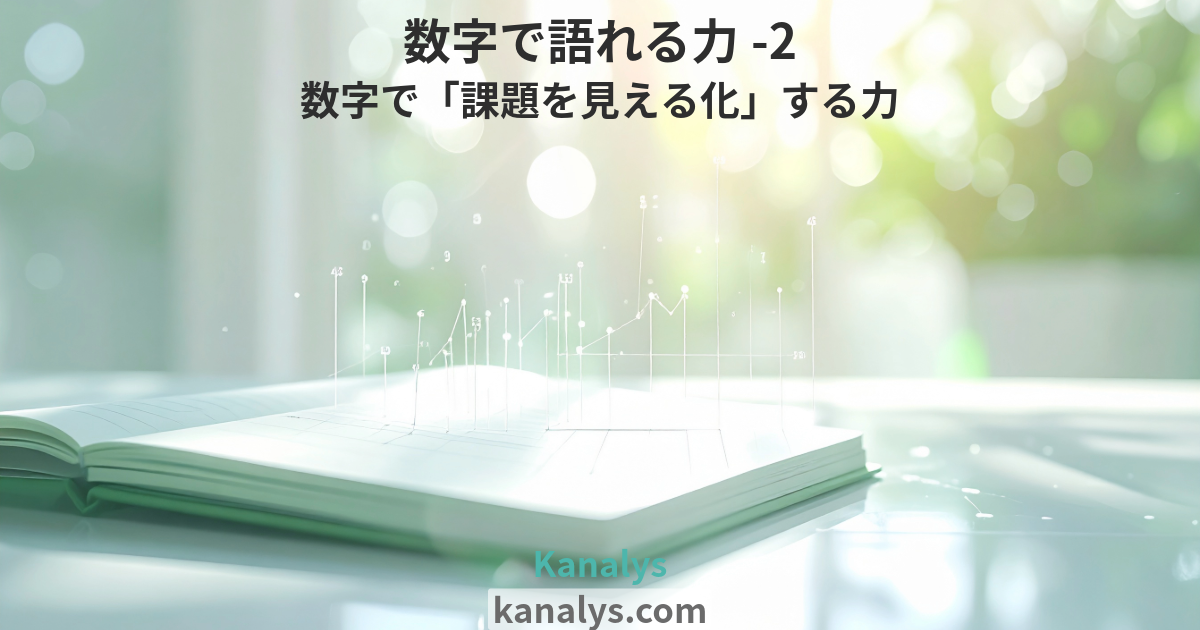── “もやもや”を数値に変えると、解決策が見えてくる
🧩 本記事は、シリーズ「数字で語れる力」第2回です。
第1回では、「なぜ数字で語る力が必要なのか」をテーマに、
“感覚では伝わらない現実”と向き合いながら、数字で語る重要性を整理しました。
今回はその続編として、「課題を数字で見える化する力」についてお話しします。
課題が“もやもや”して見えない理由
仕事でも副業でも、
「なんとなく忙しい」「成果が出ていない気がする」と感じることは誰にでもあると思います。
けれど、そうした“もやもや”は、感覚のままでは正体がつかめません。
数値に置き換えることで初めて、何が問題で、どこに時間や労力が流れているのかが見えてきます。
私はこの「見える化」という考え方を、研究開発の現場でも、副業を始める際にも、強く実感しました。
数字で見える化する意味
数字にすると「現状」がわかる
人は、感覚に頼ると“印象”に引っ張られがちです。
忙しいように感じても、実際に時間を記録してみると「思ったより集中できていた」なんてことも多い。
数字にすることで、現状を客観的に把握できるようになります。
数字にすると「優先順位」が決まる
数字で可視化すれば、「どこに力を入れるべきか」が明確になります。
すべてを同時にやろうとするより、インパクトの大きい部分から手を付ける判断ができるようになる。
数字にすると「変化」が追える
改善前後を比べて、施策がどれほど効果を持ったかが検証できます。
成長や改善を“見える形”で感じられることで、モチベーション維持にも繋がります。
実践編①:本業での「見える化」事例
研究開発業務のなかで、私はある時期から、
工程ごとの作業時間を細かく記録するようにしました。
最初は単なる習慣づけのつもりでしたが、記録を続けるうちに、
「どの工程でボトルネックが生じているのか」がはっきり見えるようになったのです。
“なんとなく時間がかかる”から、
“実際に工程Cで平均30%多く時間がかかっている” へ。
この小さな違いが、チーム全体のスケジュール調整にも大きな効果をもたらしました。
また、複数プロジェクトを並行して進めるときには、
業務負荷や納期の重要度をスコア化して可視化しました。
プロジェクトごとに「負荷指数」を算出し、
その合計値を見ながらタスクを再配分することで、驚くほど業務が整理されました。
余談ですが、こうして自分で数字を使って業務を管理してみると、
会社がKPIや定量評価にこだわる理由がよく分かります。
(もちろん、その評価手法の妥当性は別の話ですが…笑)
実践編②:副業での「見える化」事例
副業を始めようと決める前、私は長いあいだ「このままの収入で将来大丈夫なのか?」という不安を抱えていました。
けれど、それはただの“感覚的不安”でしかありませんでした。
そこで、手取り収入、支出、昇給見込み、生涯収入をExcelでシミュレーションしてみました。
数字にした瞬間、それまで曖昧だった将来像が、はっきりと輪郭を持って見えてきたのです。
「このままだと○歳時点で可処分所得はここまでしか伸びない」
「副業で月5万円を継続できれば、10年後には+600万円の余裕ができる」
数字で見える化したことで、「やるべき理由」が明確になり、
行動へと移すエネルギーが湧きました。
感情を整理するためにも、数字は欠かせないツールだと実感しました。
「数字で見える化」は目的ではなく出発点
見える化の目的は、“分析すること”ではなく、“動きを変えること”です。
数字は問題の「現状」を映す鏡であり、「次の一歩」を決めるための道具。
数字を取るだけで満足してしまっては意味がありません。
「どこに課題があるのか」「どの数字を変えるべきなのか」まで踏み込むことで、はじめて見える化は価値を持ちます。
今日からできる「見える化」習慣3つ
1️⃣ 行動ログをつける(1日5分)
→ 時間・集中度・満足度を簡単にメモするだけでもOK。
2️⃣ 感覚を数値に変換する練習をする
→ 「まぁまぁ忙しい」→「忙しさ8/10」といった具合に。
→ もちろんこれは“主観的な数値”だけれど、同じ基準で継続して記録すれば「変化の方向性」が見える。
→ つまり、客観的な絶対値よりも、“昨日より集中できたか”“先週より楽になったか”を比較することが重要。
完璧なデータではなくても、**「主観の定点観測」**は立派な分析。
感覚を数字で“固定化”することで、初めて改善の手がかりが生まれる。
3️⃣ 週1で自分の数字を振り返る
→ 「増えた/減った」を見るだけで、次の行動が変わる。
まとめ:数字で見える化できる人は、改善のチャンスを逃さない
数字にすることは、現実と向き合うこと。
最初は怖く感じても、数字を通じて初めて“改善の入り口”に立てます。
本業では、工程ごとのボトルネックを発見し、
副業では、将来の収入見通しを定量化することで、
“見えなかった問題”が、“行動できる課題”へと変わりました。
「見える化する力」は、キャリアにも副業にも共通する成長の第一歩。
そして次の記事では、その“見えた数字”をどう意思決定に活かすかを掘り下げていきます。
💡 次回予告
次回は「数字で意思決定する力」。
感情ではなく根拠で選ぶ、数字思考のフレームを紹介します。
📘 「数字で語れる力」シリーズ一覧
1️⃣ 第1回:なぜ「数字で語れる力」が必要なのか
2️⃣ 第2回:数字で課題を見える化する力(本記事)
3️⃣ 第3回:数字で意思決定する力
4️⃣ 第4回:数字で伝える力
5️⃣ 第5回:数字で成果につなげる力(準備中)